ふるさと納税の確定申告を忘れた場合の対処法!必要書類や申請方法をわかりやすく解説

ふるさと納税は、好きな自治体へ寄付を行いながら、税金控除も受けられる制度です。しかし、確定申告でふるさと納税の寄付金控除を適用し忘れると、せっかくの控除を受けられない可能性があります。
この記事では、ふるさと納税の確定申告を忘れた場合の対処法について、申請方法や必要書類をわかりやすく解説します。更正の請求、還付申告などの手続きについて詳しく説明しますので、申告忘れに気づいた方は、ぜひ参考にしてください。
ふるさと納税を行える上限額は、年収・家族構成等によって異なります。3ステップで寄付の限度額がわかる「かんたんシミュレーター」で上限額の目安をチェック!
ふるさと納税の確定申告をしないとどうなる?
ふるさと納税をした場合、寄付金控除を受けるためには確定申告が必要です。確定申告でふるさと納税したことを記載しないと、控除は適用されません。つまり、本来控除されるはずの所得税や住民税がそのまま徴収されることになり、結果として税金の負担が増えてしまいます。
確定申告でふるさと納税したことを申請しなかったとしても、ペナルティや罰則はありません。しかし、せっかくの控除を受けられないのは損失ですので、必要な手続きをおこなってカバーしましょう。
ふるさと納税で確定申告が必要な人はどんな人?
ふるさと納税を活用した人の中で確定申告が必要な人は、主に以下の3パターンです。
-
1年間のふるさと納税の納税先が6自治体以上の人
-
ふるさと納税のワンストップ特例制度の申請期限に間に合わなかった人
-
ふるさと納税と各種控除(医療費控除や住宅ローン減税など)を併用したい人
上記以外でも、「1年間に20万円以上の副業収入がある給与所得者」や、「2つ以上の事業主から給与所得を得ている人」「給料が2,000万円を超える人」「個人事業主」は、そもそもふるさと納税をしていなくても確定申告をする必要があります。基本的には、ふるさと納税を利用したら確定申告が必要ですが、ワンストップ特例制度を利用する場合に限り、不要となると覚えておきましょう。
ふるさと納税の確定申告を忘れた場合、5年以内なら「更正の請求」ができる
「確定申告でふるさと納税の記載を忘れた」という場合は「更正の請求」という手続きで、本来受けられるはずだった控除を受けることができます。
更正の請求とは、確定申告後に税額に誤りがあったり、確定申告を行わなかったりした場合に、正しい金額に訂正できる手続きのことです。国税庁のホームページから「更正の請求書」を入手して記入し、「必要書類」とともに所轄の税務署に提出すれば大丈夫です。申請から概ね1~2カ月で、指定の口座に還付金が支払われます。
なお、請求期限は「法定申告期限から原則5年以内」です。例えば、2024年分の所得の場合、確定申告の申告期限が2025年3月15日であれば「2030年3月15日」まで更正の請求が行えます。
ふるさと納税でワンストップ特例制度の申請を忘れた場合も確定申告が必要
ワンストップ特例制度の利用には「寄付した翌年の1月10日(必着)まで」に、寄付した自治体に対して申請書を送ることが必要です。
もしも、ふるさと納税でワンストップ特例制度の申請を忘れた場合、確定申告を行うことで控除は受けられます。その手順は、通常の確定申告と同じです。確定申告の期間内に、確定申告書類を作成し、所管の税務署に提出してください。
確定申告自体を忘れていても「還付申告」をすればふるさと納税の還付・控除を受けられる
「ワンストップ特例制度の申請を忘れ、さらに確定申告も忘れていた」という場合でも「還付申告」をすることで、ふるさと納税の控除と還付を受けることができます。還付申告は、確定申告とほぼ同じ手順で行います。必要書類を集め、申告書を作成し、税務署に提出しましょう。
なお、申告期限は「寄付をした年の翌年1月1日から5年間」です。例えば、2024年分の寄付の場合、「2029年12月31日」まで還付申告が行えます。
ふるさと納税で人気のおいしいお米を紹介
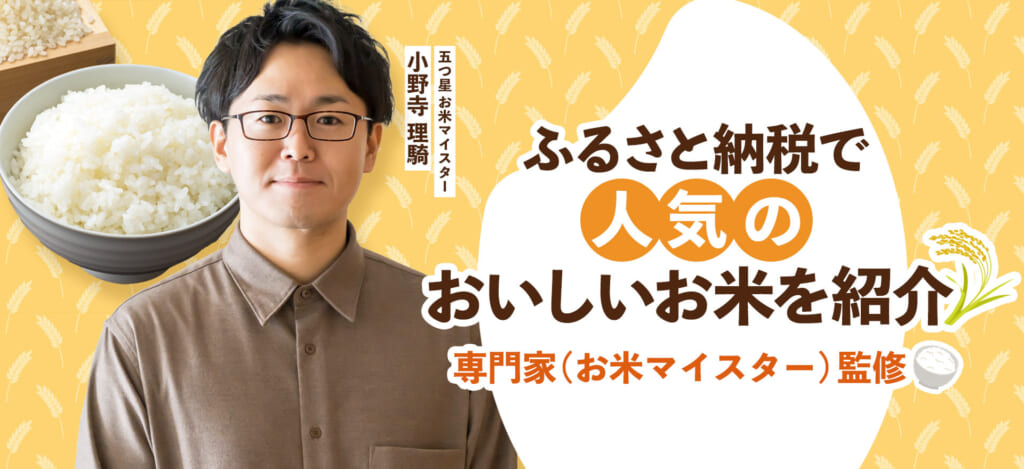
ふるさと納税でお米を選ぶなら、味・銘柄・量の違いも気になりますよね。
実は専門家が厳選した“失敗しないお米”があるんです。
特Aランクや定期便など人気の銘柄をまとめて紹介していますので、
自分にぴったりのお米を探したい方はぜひご覧ください。
更正の請求のやり方
更正の請求のやり方は、以下の3ステップです。
-
更正の請求に必要な書類を揃える
-
更正の請求書を作成する
-
書類一式を提出する
1.更正の請求に必要な書類を揃える
更正の請求を行うためには、以下のような書類が必要となるため、事前に準備しましょう。
【更正の請求に必要な書類】
-
確定申告書の控え
更正の請求書を作成する際、過去の申告内容を確認するために必要です。提出不要ですが、大切に保管しておきましょう。
-
更正の請求書
国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」からダウンロードできます。税務署でも入手可能です。
-
請求の根拠となる書類
寄付を行った証明となる寄付金受領証明書が必要です。各自治体から送付されるので、紛失しないように保管しておきましょう。
-
本人確認書類のコピー
運転免許証、マイナンバーカードなど、本人確認ができる書類のコピーが必要です。
2.更正の請求書を作成する
令和4年分以降は書式が簡素化し、更正の請求前の金額の記載が不要となりました。それでも更正の請求書は、記入事項が多いため、漏れなく正確に記載してください。

更正の請求書に記入すべき事項は、以下の通りです。
-
個人情報:氏名、住所、12桁の個人番号を記入します。
-
対象となる申告:更正の対象となる年度(令和〇年度分)と申告の種類(確定申告など)を記入します。
-
申告日:原則として申告した日を記入します。法令に規定する事実に基づく場合は、その事実が生じた日を記入します。
-
請求理由:更正を請求する理由を具体的に記入します。「ふるさと納税の寄付金控除を忘れていたため」のように明確に書きましょう。スペースが足りない場合は別紙に記載し、添付します。
-
添付書類名:更正の請求書に添付する書類名(寄付金受領証明書、確定申告書の控えなど)を記入します。
-
所得金額:所得の種類ごとに、更正後の金額を記入します。
-
所得控除額:更正後の所得控除額を記入します。
-
課税所得額:所得の種類ごとに、更正後の課税所得額を記入します。
-
税額:更正後の税額を記入します。
-
税額控除:更正後の税額控除がある場合は記入します。
-
納税額/還付金額:更正後の納税額または還付金額を計算し、記入します。
-
還付口座:還付金がある場合、振込先の銀行口座情報を記入します。
3.書類一式を提出する
作成した更正の請求書と添付書類は、確定申告を行った税務署に提出します。提出方法は、以下の3つです。
-
税務署窓口へ直接提出:窓口で直接提出する方法です。職員に不明点を質問することもできます。
-
郵送:郵送で提出する方法です。簡易書留など、配達記録が残る方法で送付できます。
-
e-Tax:国税庁のオンラインサービス「e-Tax」を利用して電子申請する方法です。自宅などから手続きできるので便利です。
なお、更正の請求には、税務署の審査があります。そのため、通常の確定申告と比べて、税金の還付が長引く場合があります。
ふるさと納税の確定申告とは?基礎知識を理解
確定申告とは、個人が1年間に稼いだ所得の金額と、それに対してかかる所得税を計算し、税額を確定させる手続きです。納めすぎた所得税を申告し、精算する手続きでもあります。
ちなみに、実際に稼いだ額が「収入」であるのに対し、収入から社会保険料や各種控除、必要経費などを差し引いたものが「所得」になることに注意しましょう。
確定申告の中で、ふるさと納税に関連する項目は「寄付金控除」と呼ばれます。納税者が国や地方公共団体などに寄付として支出した場合に、所得控除が受けられます。
ふるさと納税で確定申告をする場合はいつまでにすれば良いのか
「確定申告をする必要があるのはわかったけど、いつまでにやれば良いの?」と疑問に思う人もいるのではないでしょうか。確定申告は、1年間に生じた所得に対して、翌年の2月16日から3月15日までに申告することが必要です。
例えば、令和6年1月1日から同年12月31日の所得やふるさと納税に対する確定申告は、令和7年2月17日から3月17日までの間に申告しましょう。申告期間は1カ月ですが、必要書類を集めたり、確定申告書を記入したりすることは期間前でもできます。事前に準備しておくと、想定外のトラブルに対応できるため安心ですよ。
ふるさと納税で確定申告をしたら住民税・所得税の控除・還付はいつ?
ふるさと納税の確定申告を行った後、無事に還付・控除が適用されているかを確認しておくことも大切です。例えば、2025年1月1日から12月31日にふるさと納税を利用し、2026年2月16日から3月16日の間に確定申告をした場合、所得税の還付と住民税の控除は以下の期間で行われます。ちなみに、ワンストップ特例制度を利用した場合には、住民税からの控除のみとなるため、留意してください。
所得税の還付時期
住民税の控除時期
確定申告の場合
2026年4~5月ごろに還付
2026年6月~2026年5月の1年間控除
ワンストップ特例制度の場合
-
2026年6月~2026年5月の1年間控除
まとめ
今回は、ふるさと納税の確定申告を忘れた場合の対処法を解説しました。ふるさと納税の確定申告を忘れても「更正の請求」または「還付申告」が可能です。どちらも手続きはほぼ同じで、寄付金受領証明書や確定申告書の控え・本人確認書類などを用意し、書類を作成して、所轄の税務署に提出します。
なお、更正の請求が可能なのは「5年以内」、還付申告が可能なのは「5年間」です。請求・申告する方は、この記事を参考に早めに手続きを進めてください。
ふるさと納税を行える上限額は、年収・家族構成等によって異なります。3ステップで寄付の限度額がわかる「かんたんシミュレーター」で上限額の目安をチェック!










