ふるさと納税は何が得なの?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説

ふるさと納税に興味はあるものの「何が得なのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。ふるさと納税は、一定以上の収入を得る多くの方にとって、メリットがある制度です。
今回は、ふるさと納税のメリット・デメリットを含め、ふるさと納税の仕組みと魅力を解説。ふるさと納税に関するよくある質問にも、分かりやすく回答しています。
ふるさと納税を行える上限額は、年収・家族構成等によって異なります。3ステップで寄付の限度額がわかる「かんたんシミュレーター」で上限額の目安をチェック!

ふるさと納税は何が得なの?仕組みをわかりやすく解説
ふるさと納税の最大の魅力は、実質2,000円の負担でさまざまな返礼品がもらえることです。さらに、自分が応援したい自治体を選んで寄付することで、地域貢献もできる制度となっています。ここでは、その具体的な仕組みについて詳しく見ていきましょう。
2,000円の自己負担で返礼品がもらえる制度
ふるさと納税の最も注目すべき点は、寄付金額から2,000円を差し引いた金額が、翌年の税金から控除される仕組みです。たとえば、50,000円を寄付した場合、48,000円が税金から控除され、実質的な負担は2,000円のみとなります。
この2,000円の自己負担で、寄付額の最大3割相当の返礼品を受け取ることができるため、多くの場合で金銭的なメリットが生まれます。重要なのは、これが「節税」ではなく、あくまで税金の「前払い」であるという点です。支払う税金の総額自体は変わりませんが、返礼品という形で付加価値を得られることが、この制度の最大の魅力といえるでしょう。
また、年間を通じて複数の自治体に何度寄付をしても、自己負担額は合計で2,000円となります。10,000円を5つの自治体に寄付しても、50,000円を1つの自治体に寄付しても、控除限度額内であれば自己負担は変わらず2,000円です。
応援したい自治体を選んで貢献できる仕組み
ふるさと納税のもう一つの特徴は、寄付先の自治体を自由に選べることです。出身地や現在の居住地に関係なく、全国の自治体から好きな場所を選んで寄付することができます。
多くの自治体では、寄付金の使い道を「子育て支援」「環境保全」「文化財保護」「医療・福祉」などから指定できるようになっています。これにより、自分の関心のある分野に直接貢献できる点も、通常の納税にはない魅力です。
この制度が生まれた背景には、都市部と地方の税収格差を是正する目的があります。地方自治体にとっては貴重な財源となり、寄付者にとっては地域活性化に貢献しながら返礼品を受け取れる、まさにWin-Winの関係が築かれているのです。

あわせて読みたい
ふるさと納税の控除の仕組みとは?限度額の計算前に知るべきこと
ふるさと納税で寄付した金額は、「所得税の還付」と「翌年度の住民税の控除」という2つの方法で税金から差し引かれます。確定申告を行った場合は、所得税からの還付と住民税からの控除の両方が適用されますが、ワンストップ特例制度を利用した場合は、全額が住民税から控除される仕組みです。
ここで注意すべきは、実際に税金の恩恵を受けられるのは寄付をした翌年になるという点です。所得税の還付は早くて翌年の2月ごろ、住民税の控除は翌年6月から始まるため、一時的に手元の資金が減ることを理解しておく必要があります。
また、控除限度額は年収だけでなく、家族構成によっても変わります。扶養家族が多いほど控除限度額は低くなる傾向にあるため、事前にシミュレーションサイトなどで自分の限度額を確認することが重要です。
ふるさと納税の控除限度額の計算方法
ふるさと納税の控除限度額は「所得税からの控除額+住民税からの控除額」で計算できます。なお、所得税からの控除額と住民税からの控除額は、それぞれ以下のように計算可能です。
【所得税からの控除額】
(ふるさと納税額-2,000円)× 所得税率
【住民税からの控除額】
-
住民税からの控除(基本分)
(ふるさと納税額−2,000円)×10%
-
住民税からの控除(特例分)
特例分①、特例分②のうち低い方
(特例分①)
(ふるさと納税額−2,000円)×(100%−10%(基本分)−所得税率(復興所得税込))
(特例分②)
(住民税所得割額)× 20%
ふるさと納税の控除限度額の計算は、少々煩雑なため、シミュレーターを利用すると便利です。ふるラボの 「かんたんシミュレーター」なら、控除上限額の目安が3ステップですぐに分かります。

あわせて読みたい
あわせて読みたい
ふるさと納税のメリット!何がお得なのか
ふるさと納税には、実質2,000円でさまざまな返礼品がもらえるメリットがあります。ここでは、具体的にどのような点がお得なのかを詳しく解説していきます。
実質2,000円の負担で豪華な返礼品がもらえる
ふるさと納税の最大のメリットは、なんといっても多彩な返礼品です。各地の特産品である肉、魚介類、米、果物などの食品から、日用品、家電製品、さらには旅行券やイベントチケットまで、幅広い選択肢があります。
返礼品の価値は寄付額の最大3割相当と定められていますが、50,000円の寄付であれば最大15,000円相当の返礼品を受け取れる計算になります。自己負担の2,000円と比較すると、明らかに金銭的なメリットが生まれることがわかるでしょう。
特に日用品や食料品を返礼品として選ぶことで、日々の生活費の節約にもつながります。普段なかなか手が出ない高級食材を楽しんだり、地域の特産品を味わったりできるのも、ふるさと納税ならではの楽しみといえます。
クレジットカードの利用でポイントが貯まる
銀行振込やコンビニ決済、現金書留など、ふるさと納税ポータルサイトや自治体によって、選択できる支払い方法が異なりますが、クレジットカードで支払いをすれば、カード会社のポイントが貯められます。高還元率のクレジットカードを使用すれば、実質的な負担をさらに軽減することが可能です。
デビットカードでもキャッシュバックができます。
【デメリット】ふるさと納税の注意点と落とし穴|損する前に知ること
ふるさと納税にはさまざまな金銭的なのメリットがある一方で、正しく理解していないと損をしてしまう可能性もあります。ここでは、利用前に必ず知っておくべき注意点について詳しく解説します。
節税や減税になるわけではない
重要な注意点として、ふるさと納税は「節税」や「減税」の制度ではないということが挙げられます。多くの人が誤解しがちですが、ふるさと納税は税金の「前払い」であり、支払う税金の総額自体は1円も減りません。
むしろ、2,000円の自己負担金が必要なため、厳密にいえば通常の納税よりも2,000円多く支払うことになります。返礼品の価値がこの2,000円を上回ることで初めて金銭的なメリットが生まれるのです。
「税金が安くなる」という誤った認識で始めると、期待と現実のギャップに失望する可能性があります。制度の本質を正しく理解した上で、返礼品という付加価値を楽しむという姿勢で利用することが大切です。
控除限度額を超えた分は全額自己負担
ふるさと納税で最も注意すべきは、控除限度額の存在です。自身の年収や家族構成によって決まる控除限度額を超えて寄付した場合、その超過分は通常の寄付となってしまいます。
たとえば、控除限度額が50,000円の人が70,000円寄付した場合、20,000円はふるさと納税の対象外となり、最大で合計22,000円(自己負担2,000円+超過分20,000円)の負担となります。これでは、お得どころか想定外の出費になってしまいます。
ただし、超過分20,000円については通常の寄付となるため、確定申告時に所得税の寄付金控除の対象となる場合があります。
また、医療費控除や住宅ローン控除を併用している場合は、ふるさと納税の控除限度額が下がる可能性があります。事前にシミュレーターなどで正確な限度額を把握することが、損をしないための最重要ポイントです。
税金の控除・還付は翌年になる
ふるさと納税のもう一つの注意点は、寄付してもすぐにお金が戻ってくるわけではないということです。寄付をした時点で一時的に手元の資金が減り、実際に税金の恩恵を受けられるのは翌年になります。
具体的には、所得税の還付は翌年の2~3月以降に振り込まれ、住民税の控除は翌年6月から翌々年5月まで毎月の住民税から差し引かれる形で適用されます。このタイムラグを考慮せずに無理な金額を寄付すると、生活資金が不足する可能性があります。
特に年末にまとめて寄付する場合は、ボーナスや貯蓄の状況を踏まえて、余裕を持った資金計画を立てることが重要です。
住んでいる自治体への寄付では返礼品がもらえない
意外と知られていない落とし穴として、現在住民票を置いている自治体に寄付をしても返礼品は受け取れないという点があります。これは総務省の通達により、住民への返礼品提供が禁止されているためです。
この規制は、自治体間の過度な返礼品競争を防ぐために設けられました。自分の住む自治体がどんなに魅力的な返礼品を用意していても、それを受け取ることはできません。
返礼品を目的としてふるさと納税を行う場合は、必ず自分が住んでいる自治体以外を選ぶ必要があります。ただし、純粋に地元を応援したいという目的であれば、返礼品なしでも寄付することは可能です。
あわせて読みたい
ふるさと納税をした方がいい人・しない方がいい人の特徴
ふるさと納税は誰にとってもお得な制度というわけではありません。自分の状況に照らし合わせて、利用すべきかどうかを判断することが重要です。
【した方がいい人】所得税・住民税を納めている
ふるさと納税の恩恵を最大限に受けられるのは、所得税や住民税を納めている人です。会社員や公務員、個人事業主など、安定した収入があり、一定額以上の税金を納めている人にとっては、非常に魅力的な制度といえます。
特に年収が高く、納めている税金額が多い人ほど、寄付できる限度額も高くなるため、より多くの返礼品を受け取ることができます。一般的に、控除限度額が7,000円以上になる人であれば、返礼品の価値(寄付額の3割=2,100円相当)が自己負担の2,000円を上回るため、金銭的なメリットを享受しやすくなります。
年収300万円以上の給与所得者であれば、多くの場合でメリットがあるといえるでしょう。まずは自分の控除限度額を確認してみることをおすすめします。
【しない方がいい人】収入が低い・余裕資金がない
一方で、ふるさと納税をおすすめできないのは、そもそも所得税や住民税を納めていない、または納税額が非常に少ない人です。学生、専業主婦(夫)、年金生活者の一部など、収入が低い場合は控除されるべき税金がないため、金銭的なメリットを得ることができません。
また、収入があっても生活資金に余裕がない人も注意が必要です。ふるさと納税は一時的な持ち出しとなるため、その資金が生活に影響を与える可能性がある場合は、無理に利用すべきではないでしょう。
さらに、確定申告やワンストップ特例制度の手続きが面倒に感じる人、時間的余裕がない人も、ストレスになる可能性があります。メリットとデメリットを天秤にかけて、自分にとって本当に価値があるかを冷静に判断することが大切です。
ふるさと納税で人気のおいしいお米を紹介
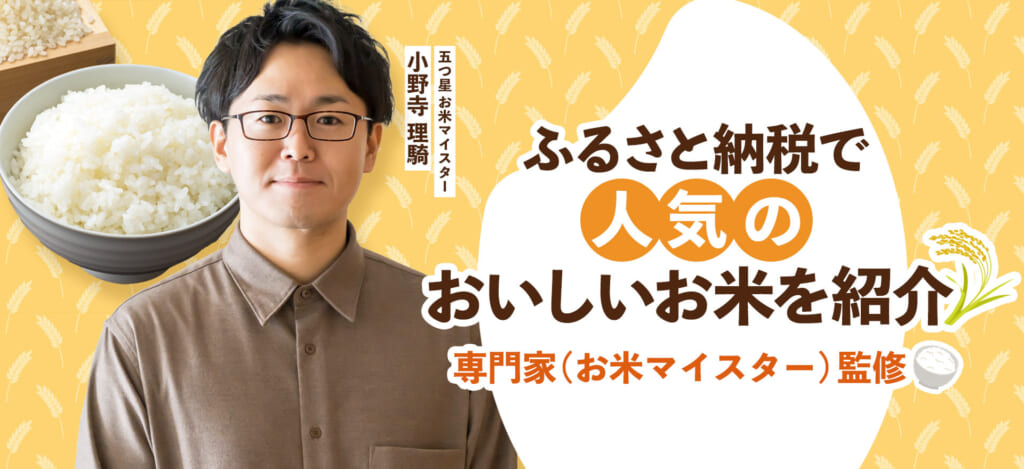
ふるさと納税でお米を選ぶなら、味・銘柄・量の違いも気になりますよね。
実は専門家が厳選した“失敗しないお米”があるんです。
特Aランクや定期便など人気の銘柄をまとめて紹介していますので、
自分にぴったりのお米を探したい方はぜひご覧ください。
ふるさと納税のやり方|初心者でも簡単な手続きの流れ
ふるさと納税の手続きは、思っているよりも簡単です。特に「ワンストップ特例制度」を利用すれば、確定申告なしで税金の控除を受けることができます。ここでは、具体的な手続き方法について解説します。
【簡単】ワンストップ特例制度の利用条件と申請方法
ワンストップ特例制度は、確定申告を行わなくても税金の控除を受けられる便利な制度です。この制度を利用できるのは、以下の条件を満たす人です。
-
給与所得者(会社員・公務員など)で、もともと確定申告の必要がない人
-
1年間(1月〜12月)の寄付先が5自治体以内であること
6自治体以上に寄付した場合は、確定申告が必要になります。
申請方法は簡単で、寄付をするたびに各自治体から送られてくる「ワンストップ特例申請書」に必要事項を記入し、本人確認書類とともに返送するだけです。最近ではスマートフォンからオンラインで申請できる自治体も増えています。ただし、申請期限は寄付をした翌年の1月10日(必着)となっているため、年末の寄付は特に注意が必要です。
【必須】確定申告が必要になるケースと手順
以下のケースに該当する人は、ワンストップ特例制度が使えず、確定申告が必要になります。
-
個人事業主やフリーランスの人
-
年収2,000万円を超える給与所得者
また、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)を受ける人も、確定申告での手続きが必須です。
確定申告の手順は、まず寄付先の自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」を大切に保管しておきます。翌年2月16日から3月15日の確定申告期間に、この証明書を確定申告書に添付して税務署に提出します。最近では、複数の自治体への寄付を一つにまとめた「寄附金控除に関する証明書」を発行するサービスもあり、手続きがより簡単になっています。
朝日放送テレビ(ABC)の「ふるラボ」は、豊富な映像コンテンツ・コラムをご用意する、ふるさと納税サイトです。初心者の方にも分かりやすいサービスを展開していますので、ぜひ「ふるラボ」で素敵な返礼品や自治体を見つけてください。

ふるさと納税に関するよくある質問
最後に、ふるさと納税に関するよくある質問に回答します。
Q.ふるさと納税が実質2,000円というのは嘘?
本当です。複数回あるいは複数の自治体に寄付しても、自己負担額は2,000円のみです。ただし、控除限度額を超えた寄付に対しては、 追加の自己負担が発生するためご注意ください。
Q.ふるさと納税はしないほうがいい?
一定以上の収入を得ている方であれば、ふるさと納税の利用にメリットがあります。一方、以下のような方は、ふるさと納税の利用を慎重にご検討ください。
-
ふるさと納税の控除限度額(利用金額)程度の余裕資金がない方
-
直近に大きな支出を控えている方
-
収入が少なく、控除すべき税金がない/ほとんどない方
-
ふるさと納税の手続きをする時間のない方
Q.ふるさと納税で損する年収は?
年収100万円前後の非課税世帯は、ふるさと納税の控除限度額が0円です。つまり、ふるさと納税を利用しても、全額自己負担となります。
また、非課税世帯でなくても「控除限度額7,000円未満の年収の世帯」は、ふるさと納税のメリットが享受できない可能性があります。
返礼品の価値は「寄付金額の最大3割」で、控除限度額7,000円未満だと、ふるさと納税の自己負担額(2,000円)を下回る可能性があるためです。
あわせて読みたい
Q.ふるさと納税をすると会社に迷惑になる?
迷惑になることはありません。
ふるさと納税しても「寄附金控除に関する証明書」などの書類を会社に提出する必要はなく、年末調整などの手間が増えることもないためです。
Q.ふるさと納税で住民税が安くならないのはなぜ?
住民税が医療費控除などで減った場合、ふるさと納税の控除限度額が圧縮され、住民税があまり安くならないケースが考えられます。
また、書類の申請や手続きに間違いがあった場合、 ふるさと納税しても税金が控除されない可能性があります。
Q.控除額の確認方法は?
実際に控除が適用されたかどうかは、「住民税決定通知書」で確認できます。この通知書は、会社員の場合は5〜6月頃に勤務先から、それ以外の人は6月頃に自治体から送付されます。
通知書の中の「寄附金税額控除額」という欄に記載されている金額が、ふるさと納税による控除額です。また、「摘要」欄に「寄附金税額控除」という文言とともに金額が記載されている場合もあります。ワンストップ特例制度を利用した場合、この金額が前年に寄付した金額から2,000円を引いた額とほぼ一致していれば、正しく控除が適用されていることになります。
Q.ふるさと納税をしたら確定申告が必要?
給与所得者の方は「ワンストップ特例制度」を利用して、簡単にふるさと納税の手続きができます。ただし、以下に該当する方は確定申告が必要です。
-
個人事業主/フリーランスの方
-
給与所得者で2,000万円超の収入の方
-
20万円以上の副収入(メインの給与以外)がある方
-
年間6つ以上の自治体にふるさと納税した方
-
住宅ローンや医療費の控除を受ける方
-
ワンストップ特例制度での申請を忘れた方 など
まとめ
ふるさと納税は、好きな自治体に寄付(納税)することで、所得税・住民税控除を受けつつ、返礼品をもらうことができる制度です。ただし、ふるさと納税には控除限度額があり、これを超えた寄付は全て自己負担となります。
会社員(給与所得者)は、ワンストップ特例制度を利用すると、簡単に寄付金控除の申請ができます。ただし、年間のふるさと納税先の自治体が6つ以上の方や、もともと確定申告の必要な方はワンストップ特例制度が利用できません。
そのため、ふるさと納税の際にはシミュレーターを利用して、控除限度額を事前に把握しておきましょう。

朝日放送テレビ(ABC)の「ふるラボ」は、豊富な映像コンテンツ・コラムをご用意する、ふるさと納税サイトです。初心者の方にも分かりやすいサービスを展開していますので、ぜひ「ふるラボ」で素敵な返礼品や自治体を見つけてください。





















